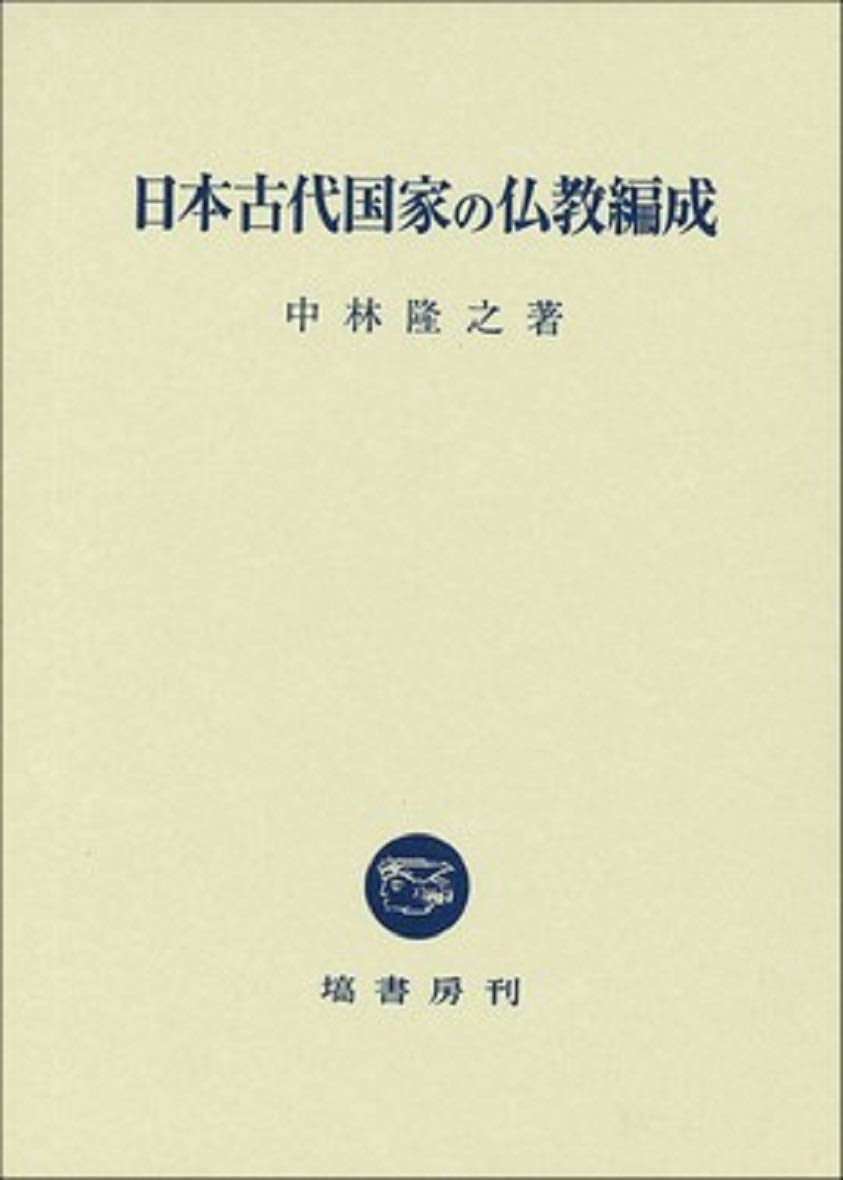想读《日本古代国家の仏教編成》
本論文は、6世紀末から10世紀はじめにいたる古代国家・王権が行なった多様な仏教政策の展開過程を、さまざまな公的法会を検討することを通じて大局的に見通し、仏教政策(編成)論を古代国家論の一部に位置づけることを目的としている。序章「問題の所在と本論文の構成」においては、通説は、国家の仏教政策を、鎮護国家呪術の効能への期待と、僧尼への外面的統制としてしか把握しておらず、国家の仏教政策の全体像が解明されていないことを指摘した上で、法会に着目して検討を加えることで通説を克服できるとの見通しを示している。第一章「古代国家の形成と仏教導入」では、倭国の仏教導入が、新羅への対抗を契機として、百済―高句麗の援助のもとでなされたことを確認している。また導入後、法興寺と諸寺で挙行された四月・七月の定期法会の意義について検討し、前者が、東アジア世界の中での自国の主権を普遍的に位置づける意味を持つこと、後者は、報恩と追善の論理で、各中央氏族の権力の世代間継承の安定と国家-王権への結集、支配層の永遠の繁栄の願望を表現したものであること、また永遠の観念の導入には、如来蔵思想が関わることなどを示している。第二章「護国経典の読経」は、護国経典にもとづく法会の機能について検討したものである。第一節「日本古代の仁王会」では、『仁王経』を用いた仁王会は、王権や国家体制の危機に際し、危機を攘うために実施されたものであり、朝鮮半島諸国に対する「大国」主義的な国威発揚儀礼としても実行された、としている。つぎに第二節「護国経典の読経」では、『金光明経』『最勝王経』は、毎年正月の法会(御斎会)で定期的に活用され、王権の統治対象たる国土と人民の安寧の祈願に用いられたこと、『大般若経』『金剛般若経』を用いた法会は、王権の拠点たる宮城を清浄化する機能を有したことなどを明らかにしている。第三章「古代王権と悔過法要」は、悔過儀礼の機能について検討したものである。第一節「悔過法要と東大寺」では、東大寺伽藍域の諸堂で実施された種々の雑密的悔過儀礼は、王権の身体擁護と近親に対する追善を主要目的としていたことをあきらかにしている。王権とつながりが深いこの地は、その後、金光明寺となり、その麓に大仏が建立され、雑密悔過もその過程で、金光明寺の護国法会や東大寺の公的年中行事法会に組み込まれ、相互に連動しあい、廬舎那仏の下での一切経法会体制の構成要素とされたことを指摘している。第二節「悔過法要と古代王権」では、仏法への王権の理念的な内在方針と神仏習合政策の推進との関わりについて考えている。天平期に新羅との関係が悪化し、天平後半には、聖武天皇-光明皇后は自身の皇統断絶への諦念を深める中で、王権は、仏法への帰依を表明するとともに、東大寺伽藍域での悔過に八幡神・若狭彦神社を参集させ、大神神社でも神仏習合を推進した。これは、神話的「大国」意識に関わる神の神仏習合を進めることで、その「大国」主義意識を、廬舎那仏と仏法の普遍の理念のもとに位置づけて保全すると同時に、神話的な国土統治観念や皇位継承理念を仏法に内在化させ、仏法を皇位・皇統の正統化理念の第一のものとする方針にもとづくものであった、としている。第四章「「華厳経為本」の一切経法会体制」では、天平感宝元年(749)閏5月に整備が命じられ、大仏開眼会によりはじまった「華厳経為本」の恒久的な一切経転読講説体制が持つ意義について考えている。第一節「南都六宗の体制的整備」および第二節「「華厳経為本」の一切経法会体制」では、『華厳経』を頂点思想とする一切経法会体制の挙行は、仏法教学の総体を『華厳経』(如来蔵思想)を基軸に「包摂」し「会通」することを意図するもので、その挙行のために南都六宗が整備されたこと、したがって、南都六宗は、通説のような学僧らの「自律」的な「学派」集団などではなく、一切経典の分担的転読講説のために造られた他律的な学僧の集団であったことを明らかにしている。また、この法会体制は、追善儀礼、誓願儀礼、護国法会、雑密的悔過などの既存の諸法会や神祇思想、宮廷儀礼を、すべて廬舎那仏と『華厳経』(如来蔵思想)の理念に包み込み、あらゆる思想の統合と「包摂」が図られた。この法会体制の整備によって、天皇を中心とする権威的な体制、「大国」意識などは、すべてそのまま肯定され、仏法総体で荘厳・聖化されたとする。第三節「聖武から空海、そして顕密体制へ」では、この一切経法会体制は、聖武朝皇統の断絶、皇位・皇統理念の仏法理念への内在化方針の放棄と、権力中枢の主導権の天皇から摂関への転換などにともなって、九世紀前半ごろまでに大きく再編された。南都六宗と天台・真言両宗の「八宗」は、宗教的自律性が容認され、宗教的達人集団として世俗権力から、仏法興隆の主導権を委任された、とする。空海は、「八宗」におけるへゲモニーの掌握と全社会的レベルでの思想・文化運動の統合をめざし、『秘密曼茶羅+住心論』において、真言教学を頂点としてその下に一切の経典と宗派・外道の理念を序列付けて組み込んで「包摂」した。その教判は、聖武朝の「華厳経為本」の一切経転読講説体制の理念を強く意識し、これを密教的に読み替えて発展させたものであった。また彼は、南都諸寺の僧や僧綱と友誼を結び東国僧とも交流する一方、世俗の宮廷文化人とも交わり、さらに自宗派の本拠で神仏習合を実践するなど、社会的思想運動の統合を図り、そのリーダーとして自らを位置づけようとしたことを示している。しかし、空海の意図は真言宗では継承されず、むしろ摂関と結んだ天台宗によって批判的に継承された。円仁一円珍一安然にいたる一大円教論は、空海の十住心教判を台密流に組み替えつつ継承したものであった。また天台宗は南都で勢力をのばす一方で、浄土信仰など社会的信仰も取り込んだ。こうして社会的権門化していった天台宗は、やがて天台本覚門を生みだし、中世顕密体制の主柱となっていった、との見通しを示している。終章「まとめと展望」では、以下の成果と課題を提示した。成果としては、第一に、国家論の一部として仏教政策(編成論)を位置づけたこと、第二に、「華厳経為本」の一切経法会体制とは、世俗権力によって仏教総体を『華厳経』〈如来蔵思想〉を基軸として権力的に教学編成することを前提に整備されたことを解明し、これがのちの仏教思想の論理構造を大枠で規定していくことになることを示したこと、第三に、研究史的に手薄であった空海の位置づけを明確化し、その結果、聖武朝→空海→台密(…顕密体制)という大きな教学的・思想編成・統合上の流れを確認できたことをあげている。また、課題としては、第一に、宮中の法会の実態解明とその位置づけをさらに解明すること、第二に、社会的レベルの仏教的信仰のありようの実態究明とその思想統合のあり方について、さらに究明しなければならないこと、をあげている。
作者:
中林隆之
塙書房
2007
- 2