世界文化遗产——长崎与天草地区的潜伏基督徒关联遗产 (2019)
Douban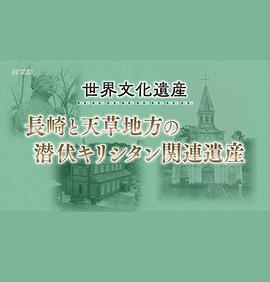
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
Übersicht
2018年6月に世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について、歴史的背景や当時の世情などを7回に亘り、映像と識者の解説で分かりやすく伝える。
第一回配信は「プロローグ編」。
Ⅱ潜伏のきっかけ…島原の乱
1637年(寛永14年)、かつてキリシタン大名が統治していた島原と天草で、大規模な宗教一揆が起こった。島原の乱と呼ばれている。キリシタン禁制が続く中、いったんは棄教していた農民達が一斉にキリシタンに立ち返り、キリスト教信仰の容認を幕府に求めて武装蜂起したのだった。三ヶ月に亘る攻防戦の後、「原城」に立て籠もった数万人の一揆勢は全滅した。そして乱に参加しなかったキリシタン達は、表向きは仏教徒を装いながら秘かに信仰を続けていくこととなった。研究者へのインタビューをを交えながら、キリシタン潜伏のきっかけとなった島原の乱について紹介する
Ⅲ潜伏…どのような信仰だったのか
江戸幕府のキリスト教禁教政策の徹底とともに一部のキリシタンは、隠れて信仰を続けていくことを選択した。禁教初期は激しい弾圧があったものの、時代が下るに連れ、信仰表明をしないという前提があれば共存と黙認もあったようである。潜伏キリシタンの信仰とはどのようなものであったのか、研究者の話を聞いた。
Ⅳ新天地…海を渡ったキリシタン
キリスト教禁教政策が続く中、開拓民が欲しい五島藩と人口増への対策を必要とする大村藩は、住民の移住協定を結んだ。この協定によって大村藩領外海地区から多くの農民が五島へと渡った。その数は三千人と言われる。外海の潜伏キリシタンたちは、新天地の島々で信仰を守り続けた。
Ⅴ終焉…信徒発見
長崎の浦上地区で隠れて信仰を続けてきたキリシタンは、外国人居留地に建てられた「大浦天主堂」の神父に信仰を告白した。1865年の事だ。これは「信徒発見」として世界に大きく伝えられた。1614年の全国禁教令以来、250年余りにわたって続いてきた潜伏キリシタン信仰はここに終焉を迎えることになる。
Ⅵ変容…カトリックに復帰
1865年の信徒発見、1868年の幕府崩壊と明治新政府発足、1873(明治6)年のキリシタン制札撤去、そして1889(明治22)年には大日本帝国憲法が発布されて信教の自由が明記された。これらの一連の出来事によって250年間の潜伏キリシタンの文化は変容することになる。潜伏キリシタンたちは、カトリックに復帰するのか、或いは復帰せずに先祖と同じ信仰を続けるのか等の選択を迫られることになった。そして住民達がカトリックに復帰した多くの集落では、喜びを表すように教会堂が次々に建てられていった
Ⅶエピローグ…潜伏キリシタンの今日的意味
長い禁教時代を経てもキリシタン信仰の在り方は変容することなく続いてきた。キリシタンは寺請制度や絵踏みを受け入れ、また非キリシタンとも折り合いながら生活をしていた。
そして江戸幕府が実施したさまざまな禁教政策は、現代の私たちにも影響を与え続けている。神社に初詣に行き、またお葬式などの法事を仏教式で行なうなどの行為は、まさに禁教によってもたらされたものだ。
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を知ることは、私たち自身を知ることにつながっていく。
長年、かくれキリシタンを調査・研究してきた平戸市生月町博物館「島の館」の中園成生学芸員に話を聞いた。